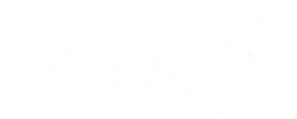老舗文房具店の役員として海外展開を担い、日本とアメリカを行き来されるさなかに六代目三遊亭圓窓師匠の落語指南所に入門。それから10年、今では自ら主催の会やプロの落語家さんとの会も含め、年間50席以上の高座を務められる「社会人落語家」に。そのバイタリティの源は?
外資系企業で仕事ひとすじの半生
もともとは音楽がバックグラウンドの「洋」の人間です。社会人生活の前半はニューヨークと日本を行ったり来たりで、音楽の輸入や海外アーティストのプロデュースなんかをやっていました。担当したアメリカのバンドのレコードがグラミー賞にノミネートされたこともあります。15年ほど前に日本の企業に移りましたが、文房具店のアメリカ展開担当となり、結局は海外出張の多い生活が続いています。それが落語とつながったきっかけは、妻とふらりと新宿末廣亭に行ったこと。人気の落語家さんが揃う中、大御所の圓窓師匠が「十徳」という噺をされたのですが、これが3日も4日も頭を離れない。妻も同様だったようで、師匠が素人対象に落語指南をされている情報を見つけてきて「一緒に習おう」と私を引っ張っていったんです。私はバンド活動をしてきたものの、芝居っけの方はゼロだし気が乗らなかったのですが…今や、こんなことになっています(笑)。
大好きな古典落語と向き合う幸せ
思えば幼い頃、進学教室でよい成績をあげると、まず母と鈴本演芸場あたりで時間を過ごした後、迎えにきた父と3人でご馳走を食べに行くのが習慣でした。その思い出に残っているのが「本寸法」っていわれる大御所ばかり。だからこそ圓窓師匠の噺が強く響いたんだと思います。そんな師匠から直に、噺から声の張り方、所作の意味まで細かに教われるのは、この上ない贅沢です。もっとも自分の落語にわずかでも自信が持てるようになったのは始めて何年もたってからです。ある時、高座を見た講釈師の友人に「どこで覚えたの、そのリズム。お客さんが思わず乗っていく」と褒められた時は嬉しかったですね。海外出張から帰国した足で高座に上がったりと、仕事との両立はしんどいこともありますが、私にとっては仕事も落語も同じくらい大切。両方うまくいくからこそ前に進める車の両輪のようなもので、気力体力の続く限りはこのスタイルを貫いていきたいですね。
私のお気に入り
男っぷりが上がるコーディネート
 やっぱり縞っていうのは粋ですよね。このはっきりとした縞の着物にドットで描いたやわらかな縞の羽織の組み合わせは、品がよくしゃれた雰囲気になります。着物を着る時は、羽織紐と衿の色合わせや帯にもこだわります。よく「きものは8割増、惚れちゃいけねえよ」なんて言っているんですが(笑)、まさにこの組み合わせは、男っぷりを上げてくれる気がしますね。ここ一番の大事な会にこそ、着たいです。とはいえ、毎年呼んでいただける会から、自分で一からつくったイベントまで、すべての高座が大切ですね。
やっぱり縞っていうのは粋ですよね。このはっきりとした縞の着物にドットで描いたやわらかな縞の羽織の組み合わせは、品がよくしゃれた雰囲気になります。着物を着る時は、羽織紐と衿の色合わせや帯にもこだわります。よく「きものは8割増、惚れちゃいけねえよ」なんて言っているんですが(笑)、まさにこの組み合わせは、男っぷりを上げてくれる気がしますね。ここ一番の大事な会にこそ、着たいです。とはいえ、毎年呼んでいただける会から、自分で一からつくったイベントまで、すべての高座が大切ですね。
おめでたい場所にもふさわしい竹柄
 初めて挑戦した大胆な竹の節の柄。茶系の着物というのも、これまで選んだことがなかったので冒険でしたが、深い色の羽織と合わせてしっくりと着こなせました。竹の柄はおめでたい席にもぴったりですし、左甚五郎の人情噺「竹の水仙」にも似合いますね。芸も竹のように伸びてほしいと願いをこめて着ます。やはり私は本寸法の落語で育ったこともあって、自分の目指す落語もそこにあります。一方で客層によって話し方を変えたり、自分の持ち時間ぴったりに仕上げるために噺を何パターンにも編集したりする工夫も、楽しんでやっています。こうしてさまざまなお客さまに披露して、「やっぱり生で聴く落語はいいわね」なんて言葉を頂戴すると報われます。
初めて挑戦した大胆な竹の節の柄。茶系の着物というのも、これまで選んだことがなかったので冒険でしたが、深い色の羽織と合わせてしっくりと着こなせました。竹の柄はおめでたい席にもぴったりですし、左甚五郎の人情噺「竹の水仙」にも似合いますね。芸も竹のように伸びてほしいと願いをこめて着ます。やはり私は本寸法の落語で育ったこともあって、自分の目指す落語もそこにあります。一方で客層によって話し方を変えたり、自分の持ち時間ぴったりに仕上げるために噺を何パターンにも編集したりする工夫も、楽しんでやっています。こうしてさまざまなお客さまに披露して、「やっぱり生で聴く落語はいいわね」なんて言葉を頂戴すると報われます。
顔色を明るくみせるソフトな色あい
 柄の中でも、市松模様が好きです。洋服は、ほとんど黒や紺、グレーしか着ないのですが、着物は明るめの色あいを選ぶことが多いです。特にこのピンクがかった羽織の色は絶妙。どんな場でもぱっと映えるので、噺なら「初天神」とか、明るいものが似合いますね。春や新年の華やかな会にもふさわしい組み合わせです。これからも努力を重ねて一つでも多くの噺を自分のものにし、お客さんと一体感の味わえる高座を務めていきたいです。
柄の中でも、市松模様が好きです。洋服は、ほとんど黒や紺、グレーしか着ないのですが、着物は明るめの色あいを選ぶことが多いです。特にこのピンクがかった羽織の色は絶妙。どんな場でもぱっと映えるので、噺なら「初天神」とか、明るいものが似合いますね。春や新年の華やかな会にもふさわしい組み合わせです。これからも努力を重ねて一つでも多くの噺を自分のものにし、お客さんと一体感の味わえる高座を務めていきたいです。